多様性社会での農山村
東京農業大学名誉教授・前学長 進士 五十八(第2740号・平成22年11月15日)
国際生物多様性年は新時代の幕開け
名古屋市の国際会議場とその周辺の交流フェア会場の賑わいは、日本の不景気風を吹きとばす勢いであった。
CBD、生物多様性条約のCOP10、締約国会議第10回。2010年10月のマスコミは正に生物多様性で盛りあがった一瞬であった。各国代表やIUCN、UNEP、研究者、そして何よりも市民NPOの姿が多い。企業や自治体、大学のテントもたくさんでていて、生物多様性への危機感はやっと本物になったかと感慨深い。
私自身も環境省の『里地里山保全活用行動計画』の検討会座長として、COP10で日本が世界に発信する「SATOYAMAイニシアチブ」への共感のひろがりを実感した。これからは間違いなく生物多様性の考え方が世界の、そして政治、経済、社会の基調となっていくだろう。また、そうならなければ、地球と人類の将来はないだろう。
もちろんCPO10の会場の賑わいや盛り上り、またマスコミのとりあげた話題の広がりだけで楽観視するわけにはいかない。世論調査では〝生物多様性?の言葉の認知度が低いと言われている。農業者の間では、特にその傾向が強いと言われてもいる。
ただ私は思う。およそ、日常語とは言い難い“生物多様性”などという学術用語をおしつけたり、〝生態系サービス”などとわかったようなわからないような言葉を使おうとする専門家の側こそ批判されるべきではないか。
“生きものにぎわい”、“たくさんの生き物の生命のつながり”、また〝自然の恵み?と言えば、誰にもわかる。ましてや、日々農業の現場で、太陽と土と水と生き物をワンセットでつきあっている農山村の人たちは、理屈ぬきに、その大切さをわかっているはずだ。
だから私はこう考える。今年、2010年の国際生物多様性年は、多くの国民、市民にとって農林地、農林業、農法などのあり方がバイオダイバシティを左右する最大の要因であることを深く認識させた、いわばこれまで都市で完結していた都市民たちの関心事が農林業や農山村エリアに大きく拡大する重要な契機となったということ。
一方、農業関係者や農政を扱う行政関係者に対しては、農業基本法、食料農業農村基本法に次ぐ第三の変革、すなわち〝生物多様性保全農業?とでもいうべき、新しい農法を全国土で展開すべきことを深く考えさせる重要な契機となった(?)。否、重要な契機とすべき年であろうということである。
農林の多面的機能の価値計算の落し穴
2001年、「農林業の多面的機能の評価」について日本学術会議が農水省に答申した。その折、ワーキングの三菱総研が「多面的機能の代替財の現在価格による貨幣価値」を試算した。農業では、洪水防止機能など多面的機能の合計は5兆5千億円/年。林業では、地表面侵食防止機能など多面的機能の合計は四七兆七千億円/年という数字を導びいた。
当事者は、農林業の大切さを国民に理解させ、その為の予算支出に非農家、サラリーマンの理解を得たいと考え、学術会議に委託したのだろう。
しかし、私は「農林」のもっている本当の価値を見誤まらせてしまうことになったと思う。
ひとつには、日本国中の農林地の存在価値が、当時大企業1社で10兆円を売上げていたことと比較して、53兆円と試算して納得するほど関係者自体が農林の意味を過小評価している点。
もうひとつは、多面的とは言え、6~7の機能で農林の総合的価値が試算できると考えるほど、科学的合理主義で安易に農業農村の価値や意義を矮小化して捉えてしまう浅薄な認識や姿勢で割り切っている点。
共に、ここに農業、農学関係者の内向きの気弱な理解度、認識方法を感じてしまう。
果して、日本の七割を占める森林や、国土の四割を占める里地里山が、国家国民にとって、その程度の存在でしかないのだろうか。
いま改めて生物多様性が叫ばれ、その切り札が「農林次第」であることを自覚しなければいけない時代には、近代科学の要素還元型の矮小化思考を反省し、「農」の現代的意義をもっと大きく捉える発想が必要である。
そのことは、農学研究者、農政関係者において最も鈍く、むしろ大都市などの市民の方が鋭いように思う。COP10の会場で出会った元気な市民、そしてそういう市民と連携して元気溌剌の農民の皆さんは、すでに「農」の現代的価値や意義を十分に自信をもって行動しておられる。
地球社会の持続性は〝多様性”から
私は生物多様性だけが大事だと思っていない。これからの地球の持続性には、自然・社会・文化のそれぞれに"多様性”が強く求められると思う。
結論を書く。自然的環境の持続性には「生物多様性」(バイオダイバシティ)が、社会的環境の持続性には「生活多様性」(ライフスタイル ダイバシティ)が、文化的環境の持続性には「景観多様性」(ランドスケープ ダイバシティ)がそれぞれ不可欠である。
先ずは、バイオダイバシティ。
生き物は自然環境に適応して生きているから、自然環境の多様性を保持することが基本になる。
熱帯雨林の伐採や砂漠化は地球環境の多様性を失わせているし、都市開発、埋立造成は国土の多様性を壊している。都市の中の高密高度化はコンクリート一色の自然の無い地域環境をつくり、生き物を生きられなくした。私が25年間かかわってきたJA東京中央会主催の「農の風景・景観コンテスト」は、この大都市東京の中にも「農」的な土地と風景を保全することが、東京の土地利用の多様性を保持し、様々な環境効果を都民生活に提供することになるとの信念で継続してきたもので、芋畑、稲田、茶園、果樹園など多様でローカリティ豊かな風景を保全している。その結果、当然バイオダイバシティはもとより、体験農園、もぎとり果樹園などで都民のライフスタイルダイバシティを支え、没個性的な大都市の地域景観を個性化しランドスケープ ダイバシティをもたらしている。
次は、ライフスタイルダイバシティについて。
これまでは、都市生活というと都心で働き近郊で寝る。働くということはサラリーマンになることでしかなかった。学校では偏差値第一であった。いずれも、働き方、学び方、ひとの生き方さえも、その時代社会の規範があって誰れもが同じ生き方を目指してきた。
末は博士か大臣か、から軍人、企業戦士まで、ライフスタイルのあるべき姿が統一的であったのだ。信仰や文化面でも同じ傾向がつづく。イスラム教徒のテロリストの問題も一神教的人生観の結果かもしれない。一方、世界的なメジャー金融資本に支配された、また極端な市場原理主義の下で“お金第1”の人生観で、かつて儒教や仏教的人生で静かに安定し、持続的であった社会を形成していたアジア人もすっかり変質してしまった。生産性の低い農業農村を捨て、工業と情報産業と都市に走った現代人も、ようやくその非を理解しはじめている。ひとりひとり自らのくらし方、生き方をチョイス(選択)できる社会。ライフスタイル ダイバシティのある社会の構築が、長い目でみた地球社会の安定につながることをわかってきた。私の近著『グリーン・エコライフ』(小学館、2010)は、そうした生き方の舞台は、都心から郊外、農山漁村のあらゆる国土、地方にあることを具体的に解説、計画論も提示している。その為には、お金で幸福になるという「経済福祉」の考え方を転換し「環境福祉」へ意識改革が必要だ。自然豊かな「美しい環境で、いい仲間たちと、いい時間を過ごすことこそハッピーだ」という考え方である。私が会長を引受けている「日本園芸福祉普及協会」は、そのひとつの展開を花や野菜づくりを通して活動。全国で数千名の会員が人生をエンジョイしている。これもひとつの生き方である。農山村は農とのふれあいの場だけでない。食や健康、越後妻有の如くアートまで多様なライフスタイルを可能にする大きな舞台である。後は、その流れをサポートする制度設計次第である。田舎ぐらし、デュアルライフ、マルチハビテーション、グリーンツーリズム、市民と農民の連携や対流等々、かなりの勢いで21世紀生活の主流化に向かっている。ただ、それが、ここまで述べてきた「ライフスタイルダイバシティ」の文明史的必然だという根本への理解を持たず、単なる商標のひとつという考えで取り組まれているために、真のニーズに応えられず前進できていない例が少なくないように思う。
高度の工業製品によって地球社会をおおい尽したいま、元来、生き物としての人間は、もはや水と緑、自然、すなわち農山村によってしか救われない。少なくとも潜在的にはこうした考え方に共感する国民が着実に増えていることを踏まえ、都市民がアクセスしやすい物心両面のサポート、制度設計が不可欠であろう。
次に、ランドスケープダイバシティ。前述のふたつの多様性をすすめれば結果的に国土全体は、多様で豊かな景観に仕上っていくはずである。ただ意図的に、景観法や条例を活用して「地域らしさ」をつくっていくことも大切である。ひとが旅をするのは、日常とは異った体験がしたいからである。政府が観光立国施策をすすめるときの基本は、日本各地をかつての三百諸侯の時代以上に「景観多様性」を実現することにあるはずだ。各地の自然、歴史、文化、生業など土地固有の景観資源を顕在化し、訪問者とのふれあい時間を高めること。そのとき、いつでも都市生活で得られない空間、景観、体験のコントラストを意識することが第1である。少なくとも“田舎”とか〝田園”の良さは、二流、三流の都市を目指す態度からは出てこない、と知るべきであろう。
私が審査委員長で今年8回目を実施した「田園自然再生活動コンクール」は、そのほとんどが都市民との連携で活発化しており、如何に多くの市民が自然はもとより農家農村と触れあいたいと思っているかがわかる。農村の受入体制や都市とのつきあい方は『実践ガイド・田園自然再生―よみがえる自然・生命・農・地域』((社)農村環境整備センター企画、農文協、2009)をみてほしい。
なお、私が都市との対比の観点から「農業農村の意義と景観の魅力と修景」について書いた『わが国農業農村の再起』(熊谷宏、進士ら、農林統計協会、2009)やその技術書『ルーラル・ランドスケープ・デザインの手法』(進士ほか、学芸出版社、一九九四)は、地域らしさの具体化のための本である。
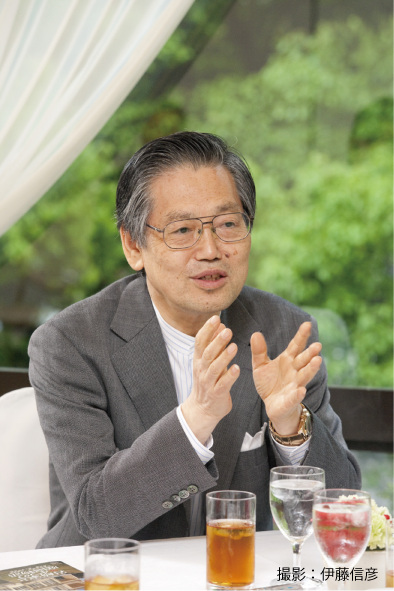
進士 五十八(しんじ いそや)
東京農業大学名誉教授・前学長、早稲田大学大学院客員教授、(社)大日本農会副会長
農学博士、造園学・環境計画・景観政策
1944年京都生まれ。これまでに東京農業大学学長、(社)日本造園学会長、(社)日本都市計画学会長、東南アジア国際農学会長などを歴任。
現在、日本学術会議環境学委員会委員長、日本野外教育学会長、自治体学会代表運営委員、政府の自然再生専門家会議委員、国土審議会特別委員、社会資本整備審議会臨時委員、環境省里地里山保全活用検討会座長、(財)水と緑の惑星保全機構理事長、(非)美し国づくり協会理事長、(非)日本園芸福祉普及協会会長、(非)みどりのゆび理事長など。
国立公園協会田村賞、日本造園学会賞、Golden Fortune表彰、土木学会景観デザイン賞、日本農学賞、読売農学賞、日本公園緑地協会北村賞など受賞。紫綬褒章受章。
主な著書『グリーン・エコライフ』(小学館)、『日本の庭園-造景の技とこころ』(中公新書・中央公論社)、『農の時代』(学芸出版社)、『ボランティア時代の緑のまちづくり』(東京農大出版会)、『都市になぜ農地が必要か』(実教出版)。
共編著『わが国農業・農村の再起』(農林統計協会)、『実践ガイド田園自然再生・よみがえる自然・生命・農・地域』(農文協)、『ルーラル・ランドスケープデザインの手法』(学芸出版社)ほか多数。
