福島県石川町/「ここに住む“人”こそまちの“宝”です」―町民ファーストのまちをめざして―

▲石川町の風景(県立石川高等学校パソコン部撮影)
福島県石川町
3310号(2025年2月17日)
福島県石川町長
首藤 剛太郎
石川町の概要

石川町は、阿武隈地域の豊かな緑と清らかな水の流れ等の美しい自然に包まれ、長い歴史と伝統を紬ぎながら、石川地方の中心都市として発展してきました。
昭和30年3月31日に、旧石川町・沢田村・山橋村・中谷村・母畑村・野木沢村が合併し、現在の石川町が誕生しました。令和7年3月には合併70周年を迎えます。
本町は、福島県中通り地方南部の石川郡中央に位置します。現在の人口は約13,800人です。面積は、115.71km²で、福島県の面積のおよそ0.84%を占めます。
標高は270mから570mで、町の北西部の阿武隈川、社川流域に広がる比較的標高の低い平坦な地域と、町の中東部、阿武隈高地の西端となる中山間地に二分されます。この中山間地を流れる北須川と今出川流域に市街地が形成され、両河川が合流する町の中央部に商店街や文教施設等が所在しています。
主要道路としては、町を縦断する国道118号線が、北は須賀川市、郡山市へと至り、南は茨城県水戸市までのアクセスを可能としています。また、町の中心部を起点に、西へは主要地方道白河石川線が、東へは主要地方道いわき石川線が走り、阿武隈地域南部の交通の要衝となっています。また、平成13年には、東北自動車道の矢吹ICと磐越自動車道の小野ICを結ぶ福島空港道路(あぶくま高原道路)の開通に伴い、町の北端に石川母畑ICが設置されるなど、主要高速道路へのアクセスも強化されています。
鉄道網としては、JR水郡線が国道118号線に沿って南北に走り、町中央部のJR磐城石川駅と北西部のJR野木沢駅を多くの町民が利用しています。
気候は、年間平均気温約14℃と比較的温暖で、降雪も少なく、風速も年間平均1.6m/sと穏やかです。
歴史

町の歴史は古く、約1万5千年前の旧石器時代後期から人々の営みが確認されています。特に鳥内遺跡は東北地方の弥生文化研究の先駆けとなる重要遺跡として福島県の史跡に指定されました。
中世には石川氏がこの地を長く支配しましたが、豊臣秀吉の奥羽仕置きにより退去させられ、領主のいない江戸時代を迎えました。石川の中心部は商工業者の集まる町となり、浜通りと中通りを結ぶ結節点、宿場として発展しました。
このような庶民による活動の中から、人々の話し合いの気風が生まれ、明治時代には東北地方最初の政治組織「有志会議(後の「石陽社」)」が結成されるなど自由民権運動の中心地として、全国的にその名が広まりました。
石川町の自然で注目されるのは、本町中心部に広がる花崗岩中から産出される鉱物です。その結晶の大きさ・美しさと種類の豊富さは国内随一で、「日本三大ペグマタイト鉱物産地」にも数えられ、中には、外国の博物館に展示されている鉱物もある程です。また、近年、日本地質学会が選定した「県の石」には、この「石川のペグマタイト鉱物」と石川町も含まれる「阿武隈高地の片麻岩」が選定され、「鉱物」そして「岩石」の町として一層知名度が高まっています。

観光・魅力PR

町の中心部を流れる北須川・今出川沿いには2,000本の桜が咲き誇り、幾重にも連なる姿は「いしかわ桜谷」と呼ばれ、多くの観光客で賑わいます。県指定天然記念物で樹齢500年以上とされる「石川の高田ザクラ」をはじめとして、町内全域に桜の巨木が多く見られ、桜の町として知られています。
また、温泉資源にも恵まれ、東北屈指のラジウム温泉として名高い母畑温泉のほか、猫啼温泉、片倉温泉、塩ノ沢温泉があり、四季をとおして多くの入湯客が訪れています。
農畜産業も盛んで、りんご、桃、梨等の果物や黒毛和牛をはじめとする多くの魅力的な地場産品が生産されています。
令和6年には町の観光物産機能を担う、一般社団法人地域商社SAKURAIZE(サクライズ)が設立され、観光振興と地場産品の魅力化をさらに推進しています。
また、令和8年には、国道118号線沿いの約20,000m²の面積を有する敷地内に、物販施設、飲食施設、情報発信施設、芝生広場、ドッグラン等を備えた、「道の駅」のオープンを予定しており、多数の人が訪れる新たな観光スポットとして注目されることを期待しています。
地域自治

昭和21年の社会教育法発布後間もない12月に、全国に先駆けて「中野公民館」が設置され、昭和26年5月までには、町内すべてに公民館が設置されました。昭和24年には、県モデル公民館に指定されるなど先駆的役割を果たし、自立進取と地域自治の精神が受け継がれてきました。
持続可能な地域運営を行うためには、そこに住む人が、自ら地域の将来像を描き、その実現に向けて必要な事柄を考え、話し合い、行政がサポートし推進していくことが重要であることから、平成21年からは公民館を自治センターへと再編し、平成28年からは地域運営組織となる地域自治協議会が町内全域に設立されました。各協議会では、地域の防犯・防災活動や環境整備をはじめ、生きがいづくりや福祉向上に加え、地域住民主体のイベント等も開催され、近年は移住・定住や農業体験を目的とした県内外からの参加者も多く、地域の賑わいの創出や特産品の開発等の地域活性化事業にも取り組んでおります。
まちなか再生

平成26年に「まちなか再生行動計画」を策定し、まちなかの拠点づくり・まちなかのにぎわいづくり・歴史・文化のまちづくり・住みやすい環境づくり・公共用地の利活用の5つの基本目標を掲げ、翌年からまちなかの活力とにぎわい創出に向けた取組をスタートさせました。
その第一歩として、まちなかの拠点づくりとにぎわいづくり、歴史・文化のまちづくりに向けた鈴木重謙屋敷の復原(平成30年供用開始)と住みやすい環境づくりと公共用地の利活用の推進に向けた旧石川小学校の減築リノベーションによる文教福祉複合施設「モトガッコ」の整備を進め、平成31年にオープンしました。
モトガッコ(文教福祉複合施設)

大人はこどもの頃から通っていた「学び舎」、こどもは今まで通い続けていた「学び舎」の両者をつなげる場「結び舎」をテーマに掲げ、「集い」・「遊び」・「学ぶ」のコンセプトからなるこの施設には、図書館、生涯学習施設、公民館をはじめ、こども子育て支援の拠点として、赤ちゃん広場や屋内遊び場、児童クラブのほか町民交流スペースがあり、工夫をこらした本施設はグッドデザイン賞も受賞し、連日多くの方々に利用されております。
廃校利活用
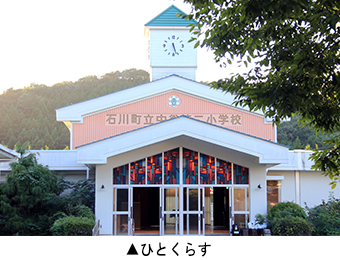
また、令和3年度には、地元の方々が校舎を思う気持ちがきっかけとなり「一般社団法人ひとくらす」を設立し、町の豊かな自然を最大限に活かす「自然環境活用型の施設」をコンセプトに、「火」と「暮らし」をテーマとしたさまざまな学習や体験と宿泊ができる施設として運営されております。
そのほかにも、小学校3校については地元の私立学校へ寄宿舎として譲渡し、県内外から多くの学生が増えたことで住民にも好影響を与えております。

まちプロ活動

本町には、県立石川高等学校と学法石川高等学校の2校が所在しており、次代を担う高校生との協働のまちづくり事業である、まちのリビングプロジェクト(略称:「まちプロ」)を平成27年から実施しています。この事業は、「まちなかに高校生の居場所(リビング)を作ろう!」という目標を掲げ、高校生が主体となって事業を考え、実施してきました。
これまで、鈴木重謙屋敷を舞台にした、高校生ワークショップ、マルシェ、屋敷内のヒバの木を活かしたクリスマスイルミネーション等、こどもからお年寄りまで幅広い年代が楽しみ、まちなかの賑わいづくりにつながるイベントを実践してきました。また、活動内容や町の魅力を発信する情報誌を発行し、多くの人にこの活動を知ってもらうよう情報を発信しています。これらの取組が評価され、平成30年には、福島県内の高校生がボランティアやまちおこしについての活動を提案する「ふくしま高校生社会貢献活動コンテスト」において、最優秀賞を、令和2年には全国過疎地域自立促進連盟会長賞を受賞しました。まちプロのスピリットは、先輩から後輩へ着実に引き継がれており、現在は、平成30年度の中心メンバー(当時、高校生)が高校の教員となり、町に戻り、まちプロの指導者として活躍しています。
こども子育て支援

本町では平成31年4月に、次代を担う町の宝であるこどもたちが心豊かに、健やかに成長できることを願い「いしかわ 子ども子育て応援宣言」を行いました。安心してこどもを産み、育てることができるまちづくりとして「子育て支援体制の充実」「子育て家庭への経済的支援」「地域における子育て支援」の3つを重点項目として各種施策を実施しています。
「子育て支援体制の充実」では、産婦人科・小児科の専門医療機関がない本町で安心して妊娠・出産・子育てができる環境整備の1つとして、妊婦や子育て世帯が、産婦人科医や小児科医、助産師とスマートフォン等で24時間相談できる「産婦人科・小児科オンライン相談サービス」を令和5年度から開始し、子育て世帯の不安の解消に努めています。また、令和6年4月には、こども家庭センターの機能を担う「こども家庭係」を新設し、町内全てのこどもとその家庭、妊産婦に対して妊娠期から子育て期まで、切れ目のない支援を提供するための体制を整備しました。
「子育て家庭への経済的支援」では、子育て・若者世帯の住宅取得支援として最大で200万円を交付する補助制度のほか、新生児誕生祝金の支給や2歳以下の児童を保育施設に預けない在宅での育児を支援する在宅育児支援金の支給、私立保育施設に通う3歳児以上の給食費の補助の実施や町立保育所・小中学校の給食費の全額無償化を行い、子育て家庭の経済的負担の軽減を図っています。
「地域における子育て支援」では、町の文教福祉複合施設「モトガッコ」で、乳幼児とその保護者を対象とした遊びや交流の場である「スキッズ広場」を運営しています。毎週金曜日には「子育て相談会」を開催し、子育てに関する相談や情報提供を行うことで、地域子育て支援拠点としての役割を果たしています。
また、町の新たな子育て支援拠点となる町立認定こども園の建設を進めており、令和7年度に開園する予定です。
福島県石川町長
首藤 剛太郎
