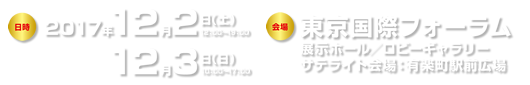STEP1情報収集はしっかり
魅力的な地域が多すぎて、移住地がなかなか決まらないという人も地域のことをもっとよく知りたいという人も、移住を成功させるために情報収集はしっかりと。
POINT 1
目的が実現できる移住地へ
移住は将来の暮らしを左右する人生の一大イベント。なんとなく田舎へ、というようなボンヤリとした気持ちだと、移住後の暮らしも見えてこない。移住の目的を明確にしよう。「農業をやりたい」、「山の近くに暮らしたい」、「古民家でカフェをしたい」など、なんでもいい。できれば具体的な輪郭線を描いて計画的に。目的があれば、それを実現できる地域や物件を中心的に調べ、現地に実際に訪れるなどしてさらに移住地を絞っていこう。自治体の「長期滞在型施設」や「短期滞在型施設」を利用するのもいいだろう
POINT 2
候補が決まっていないなら情報収集を
情報収集がもっとも手軽なのはインターネット。ある程度、候補地が絞れていれば、その自治体のウェブサイトから、地域の概要や福祉サービス、移住の受け入れ状況などを知ることができる。移住地探しはこれからという人は、田舎暮らしや移住の情報を集約しているサイトが便利。また、東京や大阪などには各県の出先機関が事務所を構えており、移住専門の窓口などもあるので、そこで相談してみるのもいいだろう。自治体やNPOの移住セミナーに参加するのもおすすめだ。
POINT 3
移住候補地を訪ねてみる
移住前にはだれでも1度は、その地域を訪れるはずだが、その際、物件や風景のいいところばかりを見るのではなく、必ず春夏秋冬1年を通して足を運び、できれば何日か滞在して、長期間過ごしてみること。自治体などが温暖とアピールしていても年間の一時期だけのこともあるし、雨が少ないといっても、いざ大雨が降ったときはどうなるかはわからない。季節や天候によって土地の状況はまるで変わるもの。風土全般をきちんと知っておくことは大切だ。
POINT 4
支援制度を過度に期待しない
移住者の受け入れに積極的な自治体では、移住奨励金の交付や住宅や子育てにかかわる補助など、さまざまな支援策を実施しているが、それを前提条件に移住先を探すのは、あまりおすすめしない。一時的な支援制度頼りでは、長期間暮らしていけない。支援が目当てだと地域に思い入れを持つのもむずかしいだろうし、住民にとっても快く受け入れられるものではない。選んだ移住先がたまたまいい支援策を実施していた、というくらいの気持ちで、あくまでオマケ程度に考えておこう。
POINT 5
移住地の下見は仲介人と
自分となんのつながりもない地域に移住の下見に行く場合は、役所の移住担当者など土地勘のある人に案内してもらうようにしよう。とくに観光客などが訪れないような小さな集落を、知らない人がうろうろ徘徊しているのは地元の人にしたら怪しいだけ。警戒されてあまりいい目では見られない。移住してそこに住むかもしれないのだから、スマートに地域になじんでいけるようにしよう。移住体験ツアーに参加するのもよい方法。参加者同士で情報の共有もできる。
移住に欠かせない4要素
自動車免許 地方、とくに田舎での移動は基本的にクルマ。会社も、買い物も、歩いていける距離にあることは少なく、バスや電車も1日に数本で使い勝手はよくない。クルマはいわば靴のようなもの。家族に1台ではなく一人1台。
お金 田舎は、都会に比べてお金をかけずに暮らせると思われがちだが、ちょっと物価が安い程度で、クルマの燃料代や寒冷地の光熱費などは都会以上にかかる場合も。仕事が安定するまで準備資金はしっかりと。
家族の同意 家族で移住する場合、積極的なのは大抵、旦那さん。しかし、先走りすぎて、家族から不満がでるケースも多い。奥さんや子どもといっしょに移住地に下見に行くなどして、納得してもらってから、移住しよう。
移住後のイメージ 地元の人に「なんでここに来たの」と聞かれたとき、目的や暮らしのイメージを言葉にできるようにしよう。きれいな空気を吸って生活したいなんていうちょっとしたことでもいい。移住成功のもっとも大切なことだ。