棚野会長をはじめとする本会役員が「クマ類の出没及び被害の未然防止に向けた対応にかかる環境省との意見交換会」に出席
令和7年11月5日、棚野孝夫会長(北海道白糠町長)、星學副会長(福島県下郷町長)、鈴木重男理事(岩手県葛巻町長)及び松田知己理事(秋田県美郷町長)は、「クマ類の出没及び被害の未然防止に向けた対応にかかる環境省との意見交換会」に出席しました。
石原宏高環境大臣は国会対応が重なったため、代理として堀上勝自然環境局長との意見交換を行ったものです。
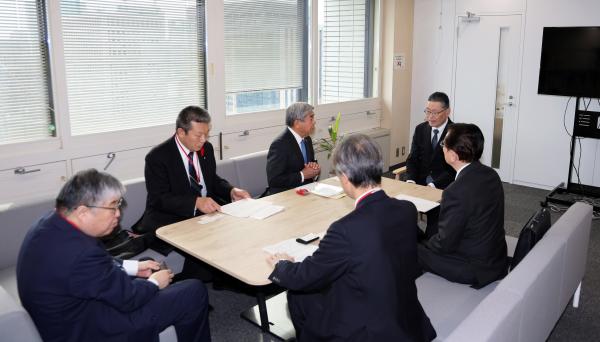
棚野会長(北海道白糠町長)は冒頭、「クマ被害はもはや災害の域に達している」と述べ、全国町村会として緊急の対応を求める意見交換の場を設けたていただいたことに謝意を示しました。全国的にクマの出没が増加している現状を踏まえ、「山間部と市街地を分けた対策が不可欠」との認識を共有しました。
また、山間部の個体数把握が不十分なままでは市街地での対応に限界があるとし、調査体制の強化を強く要望。白糠町での自衛隊協力による山の封鎖・調査の事例を紹介し、「現状把握には専門的な装備と人材が必要」と訴えました。また、麻酔銃の使用に関する制度的課題や、ハンターの高齢化による対応力の低下にも言及し、「町村ではすでに限界まで対応している」と述べました。

▲棚野会長
◇山の中のクマの個体数把握と対策の強化を
棚野会長は「クマが増えているという実感は、全国の町村で共通している」と述べ、まずは山間部における現状の把握が不可欠であると強調しました。「適正個体数が把握されていないままでは、市街地での対応も限界がある。まずは山にどれだけのクマがいるのかを知る必要がある」ものの、「役場職員が山に入って調査することは困難。ハンターも高齢化し、ライフルを持つ人材は限られている」と述べ、国による専門的な調査体制の構築を求めました。
星副会長(福島県下郷町長)は「山に残っている強いクマが繁殖を続けている。今のうちに穴グマ猟などの技術を継承しなければ対応できなくなる」と述べ、山間部での本格的な駆除と技術継承の必要性を訴えました。

▲星副会長
◇ハンター不足と麻酔銃の課題
棚野会長は「麻酔銃は獣医師など限られた資格者しか扱えず、実際には使えない」と指摘。麻酔銃の実証実験の必要性を訴え、「撃てる人材を育成するより、制度の見直しが急務」と述べました。
堀上局長は「麻酔銃は条件が限られるが、使用可能な場面を広げるための制度的検討は必要」と応じました。
◇ガバメントハンターに慎重論
棚野会長は「役場職員に鉄砲を持たせて山に入らせるのは現実的ではない。そもそも地方では公務員のなり手自体が不足している」と述べ、現場の実情を踏まえるべきだと強調しました。
松田理事(秋田県美郷町長)は「言葉が独り歩きすると誤解を生む。市町村での導入を前提とした情報発信は避けるべき」と指摘し、制度の名称や説明の仕方にも慎重な対応を求めました。
鈴木理事(岩手県葛巻町長)は「ライフルでなければクマは撃てない。狩猟免許を取った後も、実際にクマを駆除できるようになるには長期の経験が必要」と述べ、即戦力として自衛隊OBの活用を提案しました。
これに対し、堀上局長は「まずは県単位での配置を検討しており、市町村への直接的な負担は避ける方向。育成や研修については国も支援する」と説明し、制度の柔軟な運用を図る姿勢を示しました。

▲松田理事

▲鈴木理事
◇首長の責任と住民の不安
棚野会長は、「人身事故が発生した際、責任を問われるのは町村であり、マスコミ対応や住民からの苦情も深刻化している。町としてできることはすでに限界までやっている」と述べました。
星副会長は「山の中のクマの個体数が増え、里山にも広がっている。ドングリの不作や楢枯れも影響している」と述べ、環境変化による出没増加の背景を説明しました。
鈴木理事は、「かつては山菜採りやキノコ採りなど、山に入った際の事故が中心だったが、近年は人里にクマが現れ、住宅地や通学路などでの被害が増加している」と述べました。「安心してジョギングやウォーキングができない状況になっている」とし、クマの出没が人々の生活に深刻な影響を及ぼしている現状を訴えました。
◇国の対応と今後の方向性
堀上局長は「関係省庁による閣僚会議を官邸主導で進めており、11月中旬には対策パッケージを取りまとめる予定」と説明。調査体制の強化、補正予算による交付金の拡充、ガバメントハンターの育成など、具体的な対応を検討していることを明らかにしました。

▲堀上局長
